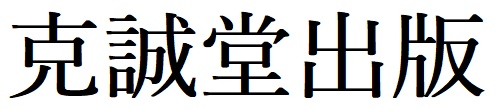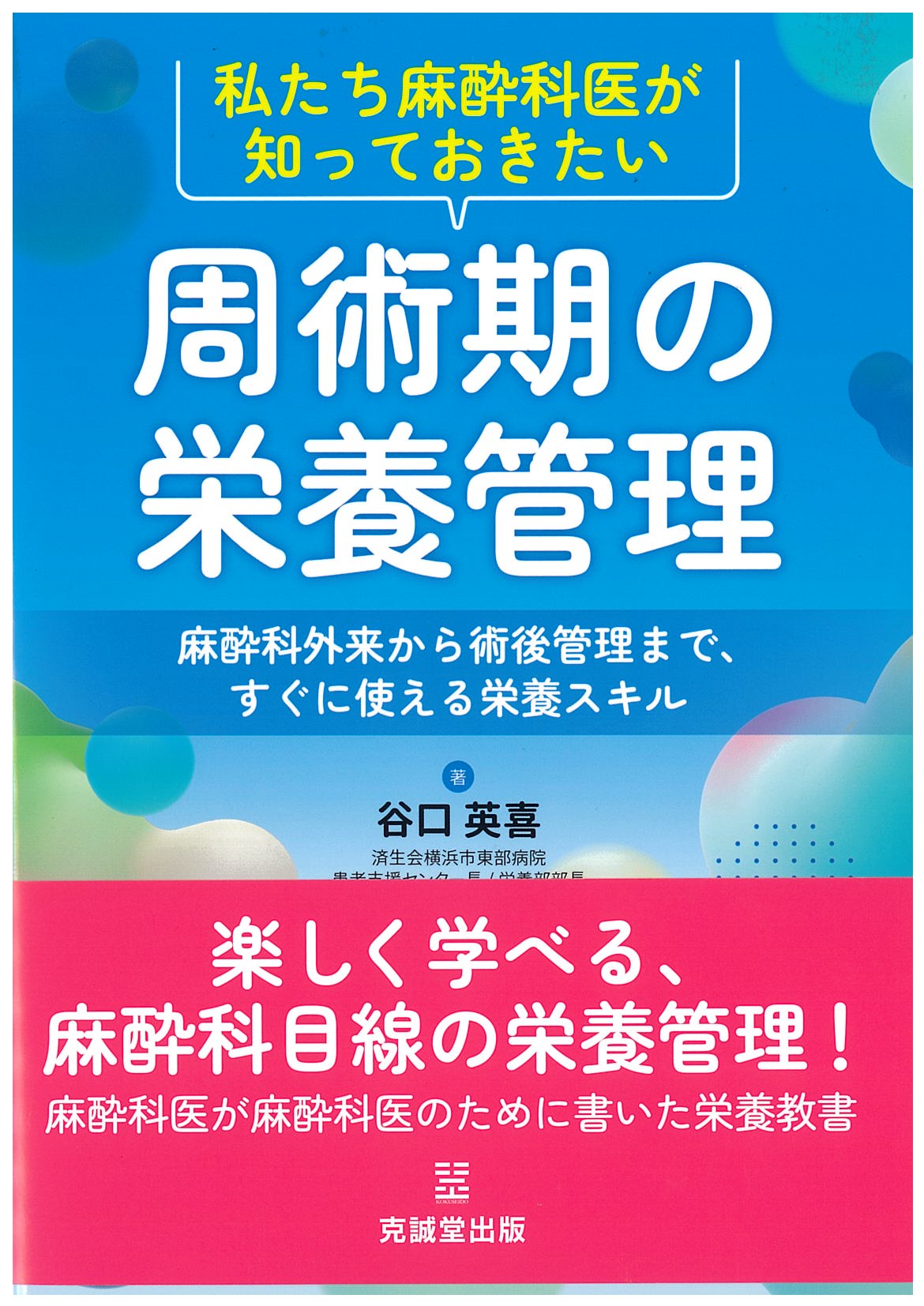私たち麻酔科医が知っておきたい周術期の栄養管理
麻酔科外来から術後管理まで、すぐに使える栄養スキル
| 著者 | 谷口英喜 |
|---|---|
| ISBN | 978-4-7719-0590-0 |
| 発行年 | 2024年 |
| 判型 | A5 |
| ページ数 | 192ページ |
| 本体価格 | 4,000円(税抜き) |
| 電子版 | あり |
M2Plus<電子版>
麻酔科医が麻酔科医のために書いた、麻酔科目線の栄養管理です。本書のコンセプトは、臨床麻酔業務に負担がかからない程度に臨床栄養学を学んでもらうことです。「Lesson 0 今さら聞けない栄養管理のための基礎知識」からはじまり、「麻酔科医だから答えられるQ&A」「栄養学に興味がわくプチ情報」なども掲載されています。“本書が、麻酔科医の先生方に気軽に臨床栄養に接することができる書籍の走りになって欲しい”という思いで企画いたしました。
Lesson 0 今さら聞けない栄養管理のための基礎知識 1
1. 含まれる三大栄養素を基に熱量は算出される 1
2. 栄養投与経路の選択基準は、“ If the gut works, use it ! ” 4
3. グル音、マーゲンチューブ、IVH なんて言葉は使わない;恥をかかないための栄養用語の再確認 14
Lesson 1 麻酔科医による周術期栄養管理が期待される術後回復促進策から学んでみよう 19
1. 術前絶飲食ガイドラインの制定で、大きく周術期栄養管理に関与 20
2. 周術期絶飲食期間の短縮、DREAM の達成支援こそが周術期栄養管理の基本 25
Lesson 2 周術期栄養管理に貢献できる麻酔管理 31
1. こんな麻酔管理がDREAM 達成の邪魔をする 31
2.栄養管理に貢献できる麻酔管理 33
Lesson 3 麻酔科外来でできる栄養状態の評価法 43
1. まずは、いつも見ている術前検査値から栄養状態が推測できる項目を知る 45
2. 他職種が使う一般的なスクリーニング・アセスメントツールを知る 47
3. 特別なシチュエーションで実施する栄養スクリーニング・アセスメントツールを知る 52
4. 世界基準となりつつあるGLIMクライテリアを知る 57
Lesson 4 術前栄養介入 63
1.術前栄養介入を実施する基準を知る 63
2.術前栄養介入法のスタンダードを知る 67
Lesson 5 麻酔管理に問題となるフレイル・サルコペニアを学ぶ 75
1.フレイルとは 75
2.サルコペニア 78
Lesson 6 間違いなくやってくる、プレハビリテーションの時代に備えて 89
1.プレハビリテーションとは 89
2.プレハビリテーションの適応判断 90
3.プレハビリテーションの実践(海外) 92
4.プレハビリテーションの実践(著者の施設) 92
5. 麻酔リスクを減らすために、高度肥満患者こそプレハビリテーション 93
Lesson 7 最新の周術期栄養管理のトレンド 99
1. 術前口腔管理から栄養管理が始まるOral care 99
2. 人工栄養は避けて、血糖コントロールを最優先 107
3. 早期経口摂取の目的は、エネルギー摂取ではない 109
Lesson 8 入院後の周術期栄養管理を実践する
①手術前日から直前まで 117
1. 術前絶飲食期間の短縮で栄養管理に貢献 糖尿病、妊婦、肥満でも実践できるか? 117
2. 術前経口補水療法(POORT) 120
3. 術前炭水化物負荷(HCHO loading) 123
Lesson 9 入院後の周術期栄養管理を実践する
②手術中から術直後まで 129
1.術前からの強制栄養は、術中はこう管理する 129
2. 麻酔科医は、実は術中栄養管理を知らず知らずのうちに実施している 132
Lesson 10 入院後の周術期栄養管理を実践する
③手術翌日以降 137
1.術直後の栄養投与経路の考え方 137
2.術直後の栄養投与の実際 140
3.麻酔管理の術後栄養管理への影響と対策 145
Lesson 11 重症患者の栄養管理 153
1. 救急・集中治療領域における重症疾患での急性期の栄養療法ガイドライン 153
2. 重症患者における栄養評価 NUTRIC スコア 154
3. 投与経路は、経腸栄養―早期経腸栄養がトレンド― 156
4.必要なエネルギー、タンパク質投与量 160
5.Refeeding 症候群 163
Lesson 12 Nutrition Support Team(NST)を知って麻酔科医もNST メンバーに 173
1.栄養サポートチーム(NST)の歴史 174
2.わが国のNST 174
3.わが国のNST の構成と業務形態 175
4.わが国のNST 活動の実際 176
5.わが国のNST の活動効果 180
おわりに 185
索引 187
「栄養管理」頻出略語 191
栄養管理と聞くと、私たち麻酔科医には縁遠く感じるかも知れない。私も、 麻酔科医局に入局した当時、まさか栄養管理に片足どころか、両足までどっぷ りと突っ込むことになるとは想像していなかった。
しかし、今では、術前麻酔科外来で栄養管理を担当し、栄養サポートチーム で栄養管理に関わり、大学院で臨床栄養の教育を担当し、こうやって栄養管理 の専門書を書く機会をいただける立場にある。
私は、麻酔科に入局後の 2 年間、臨床麻酔に関して指導を受け、さらなる興 味を抱いた。自信もつき、これからもっと自分で臨床麻酔のスキルを沢山身に つけたいと考えていた。そんな矢先に、麻酔科医になって 3 年目の人事で、希 望も予想もしていなかった救命救急センターへの派遣の命を受けた。救命救急 センターでも、緊急手術の麻酔管理を担当する機会を多々得られ麻酔科医の必 要性が実感できた。しかし、それ以上に麻酔科医が必要とされていたのは集中 治療管理であった。そこで出会ったのが、全身管理のひとつでもある栄養管理 であった。救命救急センターに入院する患者は、蘇生処置からはじまり、原因 疾患の治療、そして集中治療管理へと進む。集中治療管理では一般病棟への退 室を目指し、リハビリと栄養管理をどうやったら上手く進むかの試行錯誤の毎 日であった。結局、救命救急センターの集中治療室に 3 年、その後は本院の集 中治療室に 3 年の合計 6 年間、重症患者の栄養管理を徹底的に身につけさせて もらった。このような縁から、栄養関連の学会に参加したり、発表したりする 機会を得ることができた。そして、大きなターニングポイントとなったのが、 2006 年にウイーンで開催されたヨーロッパ臨床代謝栄養学会(ESPEN)で あった。そこで、ERAS という概念と、ERAS の創始者である Prof. Olle Ljungqvist と Prof. Ken Fearon との出会いがあった。ERAS は、栄養管理だ けではなく周術期全体を科学的根拠に基づいた工夫によって管理することで、 術後回復が促進するという画期的な概念であった。この概念は、必ずわが国の 医療にも役立つ日々がくることを確信し、学会の懇親会で Prof. Olle Ljungq- vistとProf. Ken Fearonから、わが国でも導入すべきであることを提言されたことが、私が ERAS をわが国で実現させようと決意した瞬間でもあった。その 際に、絶対に必要な医療ガイドラインが当時のわが国では制定されていなかっ た絶飲食ガイドラインであることに気がついた。ガイドラインをつくるために 術前経口補水療法を考案し臨床研究を実施した。その研究が縁で日本麻酔科学 会でも絶飲食ガイドライン作成に関われたことや、ERAS に関する教育講演を 担当したことでさらに私の臨床栄養への熱意が高まり、ついに管理栄養士の養 成校で教職をとりながら臨床栄養の研究ができる環境のチャンスをいただい た。大学では ERAS に関する研究も実施できる環境にあり、私の ERAS 熱がさ らに高まった。それは、私をこのまま ERAS を臨床で実践せずにはいられない 気持ちにさせた。その結果、臨床現場の復帰への熱望が叶い、2016 年の春に 6 年間の教員生活を終えた。臨床現場に戻り、周術期管理チームを立ち上げ夢 であった ERAS を実践し、麻酔科医として術後の飲食を促進する目的で術後疼 痛管理チームを立ち上げ、現在に至っている。振り返ると、私の麻酔科医人生 は臨床栄養学に支えられた30余年であった。私は臨床栄養と出会えたことで、 外科医や他職種との共通の話題が増え、チーム医療の醍醐味を存分味わうこと ができている。この醍醐味を、私は、もっともっと多くの麻酔科医の先生方に 広く共有してもらいたいと思い、本書の執筆に至った。
本書のコンセプトは、臨床麻酔業務に負担がかからない程度に臨床栄養学を 学んでもらうことである。栄養学の成書にはとてもレベルが及びはしないもの の、現場で臨床栄養の会話に交わるには必要十分なレベルと自負する。そして、 臨床栄養の知識が、先生方の麻酔スキルに必ずプラスの味付けをしてくれるこ とを確信する。読者の先生方には、本書を手にしたいただいたことに深謝する とともに、麻酔科目線の栄養管理を楽しく学んでいただければ幸いである。そ して、私が様々な周術期栄養管理に関する学会活動を通して持った確信、“麻酔 科医を巻き込むこと抜きにして質の高い周術期栄養管理はできない”ことを、 先生方にも自身を持って公言していただきたい思いである。
2024 年 6 月吉日
済生会横浜市東部病院患者支援センター長/栄養部部長 谷口 英喜